都営大江戸線両国駅A3・A2出口より徒歩3分
すみだ北斎美術館より徒歩3分
Open 月~土 9:30~20:00 日 9:30~18:00
Close 毎週火曜日/第3日曜日/祝日
便秘
〈 便通異常 〉
「便秘薬にさよなら!」
毎日のリズムが滞ると、なんとなく気持ちまで重たく感じませんか?
便秘は、単なる腸の働きの問題ではなく、
“カラダ全体の巡りのサイン”。
東洋医学では
「気(エネルギー)」「血(けつ)」「津液(しんえき=体のうるおい)」の流れの滞りが、便秘の背景にあると考えます。
疲れ・ストレス・冷え・ホルモンバランスの乱れ…。
Pranaでは、ひとりひとり違う「根っこ」を見つけることで、
腸だけでなく、心も肌も軽やかに調うケアで
自然な便通を取り戻します。
01.東洋医学から見た便秘
東洋医学で便秘は「大便秘結」と言われています。
排便に時間が掛かる、便意はあるのに出ないという状態です。
臓腑に熱がこもる・氣(エネルギー)がない・冷え・「氣血水」のアンバランスが原因で起こることが多く、
4つのタイプに分けられます。

02.Pranaの便秘改善施術Point!
「カラダの流れを取り戻す!スルっとスムーズなお便りを」
のための“オーダーメイド”。
毎回のカウンセリングにより心身の状態に合わせて組み立てます。
〈施術ポイント〉
🔹鍼灸治療:腰部・腹部中心
-
使用する代表的なツボ:基本経穴(ツボ):天枢、大腸兪、神門、水分など
-
置鍼時間:約5〜15分。
*置鍼時間とは、刺鍼した鍼を一定時間置いておく療法時間のこと。刺激の調整のほか、血行促進、筋肉の緊張緩和、鎮痛効果、自律神経の調整などが期待できます。
🔹アロマセラピー カウンセリングにより香りを選んでいただき、都度調香。
-
精油:フェンネル・パチュリ・ゼラニウム・クラリセージ・ラベンダー・スィートオレンジなど
-
手技:リラックスアロマセラピー・リンパドレナージュ・経絡トリートメント・ホットストーン
-
五行体質チェックとカウンセリングを基に五行ブレンドをチョイスします。


















03.あなたの便秘の東洋街区的原因は?
当てはまる項目が多いタイプが、今のあなたの状態です。気になるタイプをチェックしてみましょう。




💡 チェックの多いタイプが、あなたの今の体の傾向です。
トラブルの原因は季節やストレス、年齢によって変わることもあります。
今のあなたの体の“声”を知ることで、ケアの方向性が見えてきます。
タイプはめやすで、1つのタイプだけとは限らず、混在します。
その他便通以外の現れている症状を診ながら、治療を進めていきます。
04.お客様の声
週1~2回しかなかった便通が徐々に改善し、週4回に!お腹も軽くなり、肌の調子もUP!気力もわいてきました!(20代会社員/虚秘タイプ)
2週に1回のペースで通い、よもぎ蒸しと鍼で冷えが楽になったと思ったら、便秘薬ナシで朝スッキリ出るようにもなりました!(30代ママ/冷秘タイプ)
仕事ストレスで便秘&イライラが。施術後はお腹が軽くなり“怒り”も減りました!生理も順調になり一石二鳥です。(40代女性/気秘タイプ)
辛い物が好きだった私でも爽快感◎黄色い便も臭いも解消しました!辛い物欲も減って不思議な感じです。酵素腸活も同時にしたせいか痩せました!!(50代フリーランス/熱秘タイプ)
05.よくある質問
Q:何回通えば良い?
A:まずは2週間に1回を5回、体質改善後はメンテナンスで月1回が目安です。腸活も同時に進めると、効果大です。
Q:便秘薬を飲んでいますが大丈夫ですか?
A:可能ですが、鍼灸の効果を感じる為にも、少しずつ減薬することをおすすめしています。
Q:生理中・妊活中でも受けられる?
A:もちろん可能です!体調や体質に応じた施術をご提案します。
Q:妊娠中でも大丈夫?(冷えや妊娠中…)
A: 体調を見ながら、温め中心のよもぎ蒸し+ソフト鍼治療やアロマなど妊娠中でも可能な方法で対応させていただきます。
ご相談ください。
▶便通のしくみ
〜「出す」って、実はすごく大事なこと〜
食べたものは、胃や小腸で消化・吸収されていくうちに、液状のドロドロした状態になって大腸へ送られます。
そこで大腸がゆっくりと水分を吸収していくことで、固形の便へと変化していきます。
この便が、スムーズに肛門へと運ばれるためには、「ぜん動運動(ぜんどううんどう)」と呼ばれる腸の動きが必要です。
この動きは自律神経によってコントロールされており、たとえば食事をとると胃に刺激が入り、「さあ、動き出すよ!」という合図が腸に伝わります(これを胃・結腸反射といいます)。
さらに便が直腸に届くと、「そろそろ出そうかな?」と脳に合図が届き、排便の準備が整います(これが排便反射)。
「お通じが来た!」というのは、カラダの調子が整っている証でもあるんです。
でも、ストレスが続くとこの自律神経の働きが乱れてしまい、腸がうまく動かなくなるんです。
その結果、便が長く大腸にとどまって水分が吸収されすぎ、便が硬く小さくなってしまう。これが「便秘」の始まりです。
便通が長くない時は、カラダやココロがちょっと疲れているサインかも。
「なんとなく調子が悪い」の裏に、便通の滞りが隠れていることもよくあります。

▶便秘とは
便秘とは、正常時に比べて便通の回数が減少・排便間隔が不規則になった状態の事です。
ご自身の体調に不調を感じない状態であれば、回数などは決まりはありませんが、
-
便が硬くて出しづらい
-
いきんでもスッキリ出ない
-
便意はあるのに出ない
-
お腹が張る・ゴロゴロする
-
出た後も残便感がある
こういった状態は、「便秘」と考えられます。
特に3日以上排便がない、5日以上不快感が続く場合は、カラダのリズムが乱れているサイン。
「毎日出ているけどスッキリしない…」というのも、実は便秘かもしれないのです。

▶現代医学的便秘
現代医学では、便秘は《急性便秘》と《慢性便秘》に分けます。
原因は様々ですが、生活習慣や間違った食生活(ダイエット)、運動不足・ストレスなど原因は多岐に渡ります。
鍼灸治療適応は慢性便秘①機能性便秘になります。
《 急性便秘 》
①機能性便秘:一過性の単純便秘のこと。
原因)旅行など環境が変わったり、食事量が変化(食べる量が少ない)
②器質性便秘
原因)主に疾患
腸管内狭窄:腸閉塞、急性虫垂炎、直腸の急性炎症
腸管外狭窄:腸腔内器官の炎症、急性代謝異常、急性心不全、感染症などの時に起こる
《 慢性便秘 》
①機能性便秘:鍼灸治療適応
弛緩性便秘
腸の運動機能(蠕動運動)低下により、大腸内に長時間とどまり、水分が過剰に吸収されることでおこります。便は「太い」「硬い」「コロコロ」が特徴。高齢者や経産婦に多く見られます。
原因)運動不足・水分不足・食物繊維不足・腹筋力低下・ダイエットや薬物
直腸性便秘(習慣性便秘)
便意を抑制する習慣で起こり、女性や子供に多く、寝たきりの方や高齢者にも増えています。便が直腸(肛門の手前)に来ているのに「便が出かかっているのに出ない」「便をした感じがしない」「少し便意はあるけどタイミングを逃すと一向に出ない」などの症状があります。出口に詰まっているような感覚です。
原因)排便を我慢する
痙攣性便秘
腸の痙攣(強く収縮してしまう)による便の通過不良で起こります。弛緩性便秘と同じように大腸内に長時間便がとどまることで水分が過剰に吸収され、コロコロと硬い兎糞状の便が出るのが特徴です。(弛緩性便秘とは原因が異なります)
原因)精神的ストレス・過敏性腸症候群(IBS)・環境の変化
②器質性便秘:
原因)主に疾患
腸管内狭窄:腫瘍、炎症、術後の癒着、腸の形成異常
腸管外狭窄:腹腔内臓器の腫瘍や炎症、術後、ヘルニア
③症候性便秘:代謝、内分泌系疾患(甲状腺低下、糖尿病)、膠原病など
医療機関での治療が必要です。
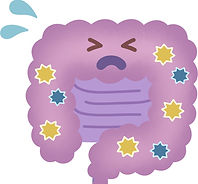
▶女性に便秘が多い理由
便秘に悩む方は、男性より女性の方が多く、また、高齢者ほど多い傾向です。
女性に多い理由は
①身体的理由:女性は腹筋が弱いため、大便を送り出すチカラが弱い
②ホルモン:性ホルモンの働きが大きく作用します。「黄体ホルモン:プロゲステロン」はカラダに水分や塩分を溜め込む働きがあり、腸壁から水分を吸収するため、便が硬くなりやすくなります。そのため、月経前や妊娠中に便秘になりやすくなります。
「卵胞ホルモン:エストロゲン」は、皮膚や粘膜に潤いを与える働きがあります、粘膜である腸壁の潤いにも関わります。更年期になりエストロゲンの分泌減少により便秘になる方が増える要因となります。
③ダイエット:食事量を減らすことにより、便の材料が減少する事と、代謝に必要なビタミン・ミネラル・食物繊維や水分・脂肪分が減少するため、腸の蠕動運動などに影響し、便が硬く、排便しずらくなります。
④精神的理由:トイレに行くことの恥ずかしさを感じることが多く、また、周りへの気遣い(仕事が忙しい、仕事のキリが悪いなど)をする女性。そのため、トイレへ行くことを我慢してしまう事が多い。また、旅行など環境の変化に敏感な方が多いため、ストレスとなり便秘につながります。

▶便秘の影響
便秘は、不要なものが体内に残って知る状態。そのため、カラダに様々な変化が起こります。
*自律神経が乱れる
*疲れやすい・疲労感がつよくなる
*うつ状態
*感染症にかかりやすくなる
*冷え症になる
*痩せにくくなる・太りやすくなる
*浮腫みやすい
*肌トラブル(肌荒れ・乾燥・ニキビ・吹き出物・シワ・シミ・くすみなど)
*腹部が張る
*下腹部で音が鳴る
*食欲不振
*吐き気
*めまい
*おならがふえる・臭う
*肩こり
*口臭・体臭がきつくなる
*血便
*痔
などなど、腸内環境が悪化することであらゆる症状を引き起こします。
▶下痢とは?
便の中の水分量が多くなり、形を失い、液状や泥状になった状態。
通常より柔らかい状態は「軟便」と言います。
腹部の不快感や腹痛を伴ったり、排便回数が増えることが多くなります。
大腸の動きが異常(蠕動運動が活発)になると、大腸内の内容物の動きが早くなり、水分を吸収できず下痢や軟便になります。
また、大腸内の水分調節の異常が起きた時も便中の水分量が増して、下痢や軟便を引き起こします。

▶東洋医学的下痢
東洋医学で下痢は「泄瀉(せっしゃ)」と言い、泥状もしくは水溶性の便で、回数が多く、渋り腹(便意があるのに出ないもしくは少量)でないことです。
タイプは5つ。
タイプ1:外邪(寒湿/湿熱)
気温や湿度など外からの要因(寒・湿・暑・熱)によって脾に負担がかかり起こる下痢。
〈寒湿〉
□寒がり □冷え症 □寒気がする □発熱 □むくみやすい □水様便
□便の臭いはない □腹痛 □お腹(腸の辺り)が鳴る
〈湿熱〉
□急迫する □便が臭い □肛門に熱感がある □口が渇く □のぼせ感がある
タイプ2:傷食(しょうしょく)
食べ物による下痢。
原因は、食べ過ぎ、冷たい飲食、生もの、脂っこい物などです。
□粘り気のある便 □未消化の物ある □便が臭い □お腹が張る □食欲がない □気持ちが悪い
□げっぷが出る □胃から上に上がる感じがある
タイプ3:肝鬱
ストレスによりおこる下痢。
強いストレス、長期のストレスが主な原因です。
□ストレスを抱えている □緊張することがある □胸~喉の辺りに詰まり感 □ため息が出る □げっぷが出る
タイプ4:脾胃虚弱
消化吸収がうまくできずに起こる下痢。
もともと胃腸が弱い事や食生活の乱れ、疲労などにより起こります。
□泥状便 □倦怠感がある □食欲がない □顔色が悪い(黄色っぽい)
タイプ5:腎陽虚
排泄を司る臓=腎の陽気が足りずに起こる下痢。
冷えにより下腹部や手足が冷えていることが多く、明け方に起こりやすいのも特徴です。
□未消化の便 □早朝に多い □お腹が冷たい(冷える) □手足が冷たい(冷える) □腰から足がダルイ
▶現代医学的下痢
現代医学的には急性と慢性があります。
下痢の多くは疾患や感染症などによるものが多いため、鍼灸治療・鍼灸&アロマセラピーの適応は、以下の場合になります。
《 急性 》
①一過性下痢:気温変化、冷え、食事の後などにおこる
原因)エアコンによる冷え、気温低下、冷たい物の飲食、飲酒、食べ過ぎなど
②心因性下痢:学校、会社に行く前、試験・受験・会議・面接など大切なイベントの前に起こる
原因)精神的ストレス
《 慢性 》
①症候性下痢:過敏性腸症候群
原因)明確ではないが精神的ストレスや自律神経の乱れなど
▶下痢の影響
下痢は、便と共に水分が排出されています。水分と一緒にミネラルも排出されています。
また、腸内の通過が早いため、栄養も十分吸収できない状態です。
*脱水
*栄養障害
*体力ダウン、倦怠感
*肛門周りの炎症(痛みや切れ痔など)
などの症状が現れます。





